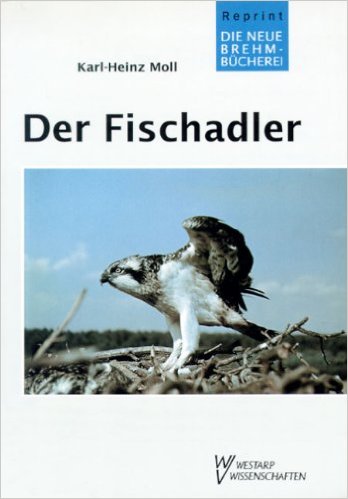ミサゴは「魚鷲」
少し古い本ですが、1962年に出版された「ミサゴ(Der Fischadler)」という本に、興味深い生態が書かれていました(図1)。ドイツ語なのでなかなか日本では知られていないこともあると思い、その一部を紹介します。「Fischadler」は直訳すると「魚(Fisch)鷲(Adler)」となり、ドイツではタカではなく、ワシの仲間とみなされていることがわかります。著者のカール・ハインツ・モル氏はバルト海に面したドイツのメクレンブルク州で、ミサゴの巣の中が見える場所にブラインドを張り、主に1950年代にミサゴの生態調査を行ないました。この地域はベルリンの北に位置していて、冷戦時代は東ドイツ領でした。以下は、その内容の一部をまとめたものです。
魚の頭と寄生虫
ミサゴはアフリカの越冬地からドイツの繁殖地に3月の下旬に渡ってきます。メスが先に到着し、オスはそれから数日遅れてやってきて、つがいで繁殖活動に入ります。子育ての期間はもっぱらオスが狩りを行ない、巣へ魚を運びます。オスは捕った魚をメスに渡す前に、たいてい頭の部分を自分で食べてしまうので、巣に持って来る魚は尾は付いていても頭付きではありません。当地では、ミサゴは魚の腸を食べないそうです。頭を激しく振って嘴に付いた腸を振り払っている姿も観察されています。魚の内臓と一緒にサナダムシのような寄生虫を体内に取り込まないようにするためだろうと、著者は推測しており、実際に、営巣木の下に落ちていた大きな寄生虫を発見しています。一方、怪我をしたミサゴの幼鳥を放鳥するまで著者が世話をしたときには、特に魚のレバー(肝臓)を好んで食べました。
ミサゴと漁業被害
調査地は旧東ドイツの有数のミサゴの繁殖地ですが、それだけに、地元の漁民との軋轢が大きくなっていました。漁協はミサゴが捕食した魚を目視観察(図2)して、それに基づいて魚の重量を推測し、そこに金額を掛けて、被害額を試算していました。そこで、著者はミサゴが落とした魚をミサゴの本剥製に持たせて写真を撮って魚の大きさを推定し、その結果を漁協の担当者に見せたところ、漁協の推定が重すぎることがわかりました。著者は保護の観点から、営巣木の周辺で収集した魚の残滓やミサゴの体長(約60 cm)を尺度にして、獲物の大きさや種類の推定を行ないました。そして、長年にわたる観察の記録に基づき、繁殖期に1羽のミサゴが1日に必要とする餌の量を魚に換算して300 gと算出し、漁協による漁業被害額の算出方法の誤りを指摘しました。
著者はミサゴが必要とする餌の量を慎重に評価し、ミサゴが病気に罹った魚を捕ることによって、魚の個体群の健全化に果たしている役割に比べれば、漁業に与える被害は問題にならないと結論を出しています。その一例として、漁師がミサゴを追い払うために営巣木を伐採したところ、地元のコイに腹水症という病気が広がってしまい、ミサゴを追い出したことを悔やんだという話が紹介されています。また、成長に支障が出る病気に罹っていると見られる小さなコイ科の魚類を巣へ運んできたミサゴの写真も披露しています。
採食時の事故
前述したように、ミサゴが1日に捕食する平均的な魚の重量は300 gと見積もっていますが、時には3 kgを超えるような大物を捕まえて、獲物から足の爪を外すことができずに、溺れ死んでしまう個体もいたそうです。ミサゴの足の爪は魚をしっかりと掴めるように、猛禽類の中で最も湾曲していますが、それが皮肉にも命取りになってしまうことがあるのですね。さらにショッキングな事故の例として、上空からダイビングしたとき、水中にアシの茎が立っていて、その茎に文字通り串刺しになり、絶命したミサゴの話も紹介されています。
食べるのは魚だけじゃない
主に魚を捕食するミサゴも訓練を行えば、オオタカやハヤブサのように鷹狩に使えるということです。
ちなみに、ミサゴは、上空から豪快に水中にダイブして、魚を捕る魚食性の猛禽というイメージが強いですが、魚だけではなく、たまには(口直しに?)、ジリスやネズミなどの齧歯類、カエルなどの両生類、オオバンやカモメ、コクマルガラスなどの鳥類を捕食することもあります。
1950年代の東ドイツといえば終戦直後であり、ソ連の占領下で自由が束縛されていたのではないかという印象がありました。しかし、これだけ詳細に猛禽類の生態を観察した人がいたことに驚きました。当時、日本ではこれほどの生態観察をした記録は少なくとも出版されていないのではないかと思います。イギリスやドイツには、このような種別の専門書が多数出版されていますが、日本では、こうした研究書があまり見当たらないのは残念なことです。